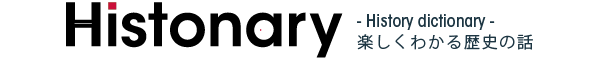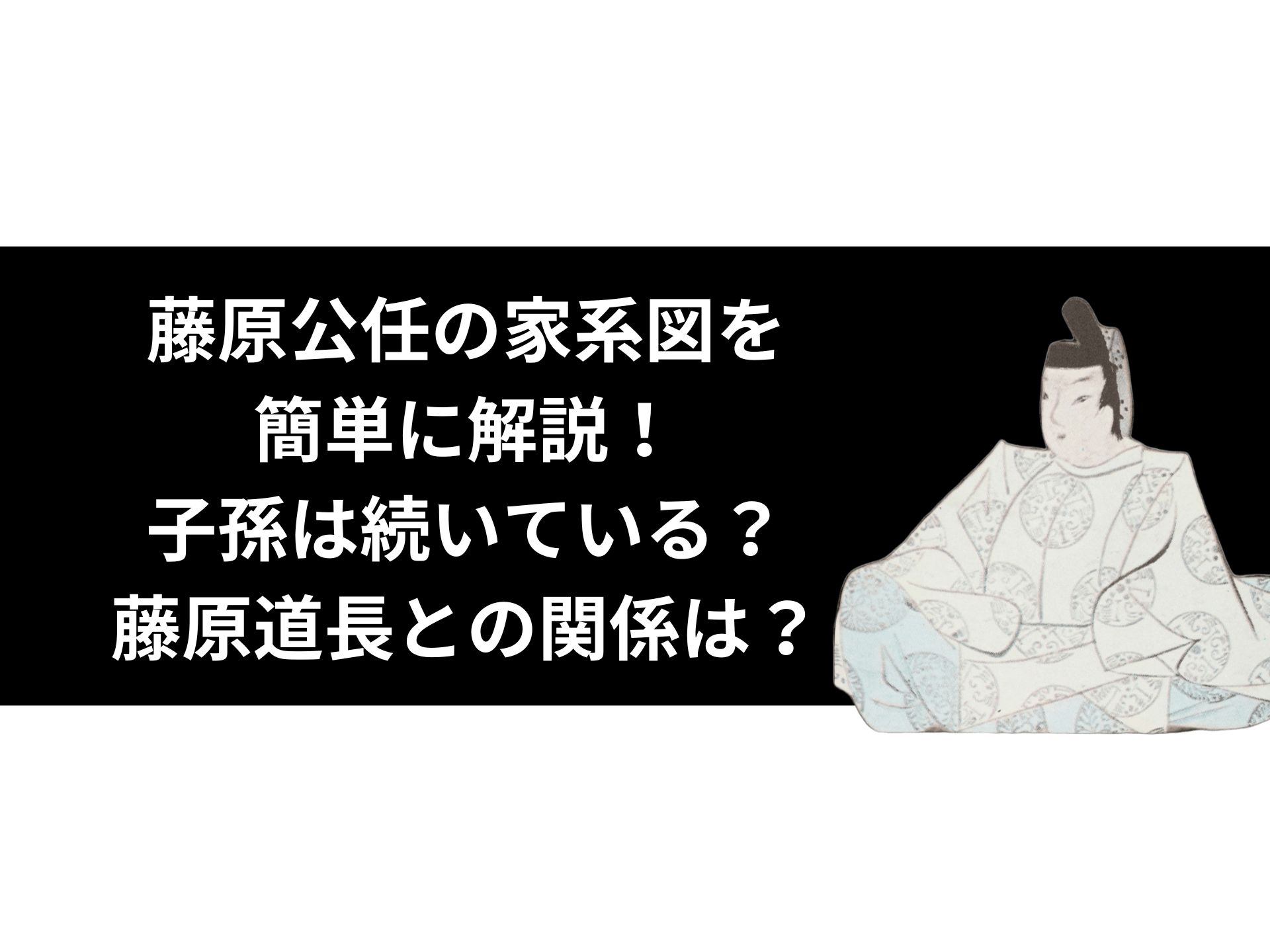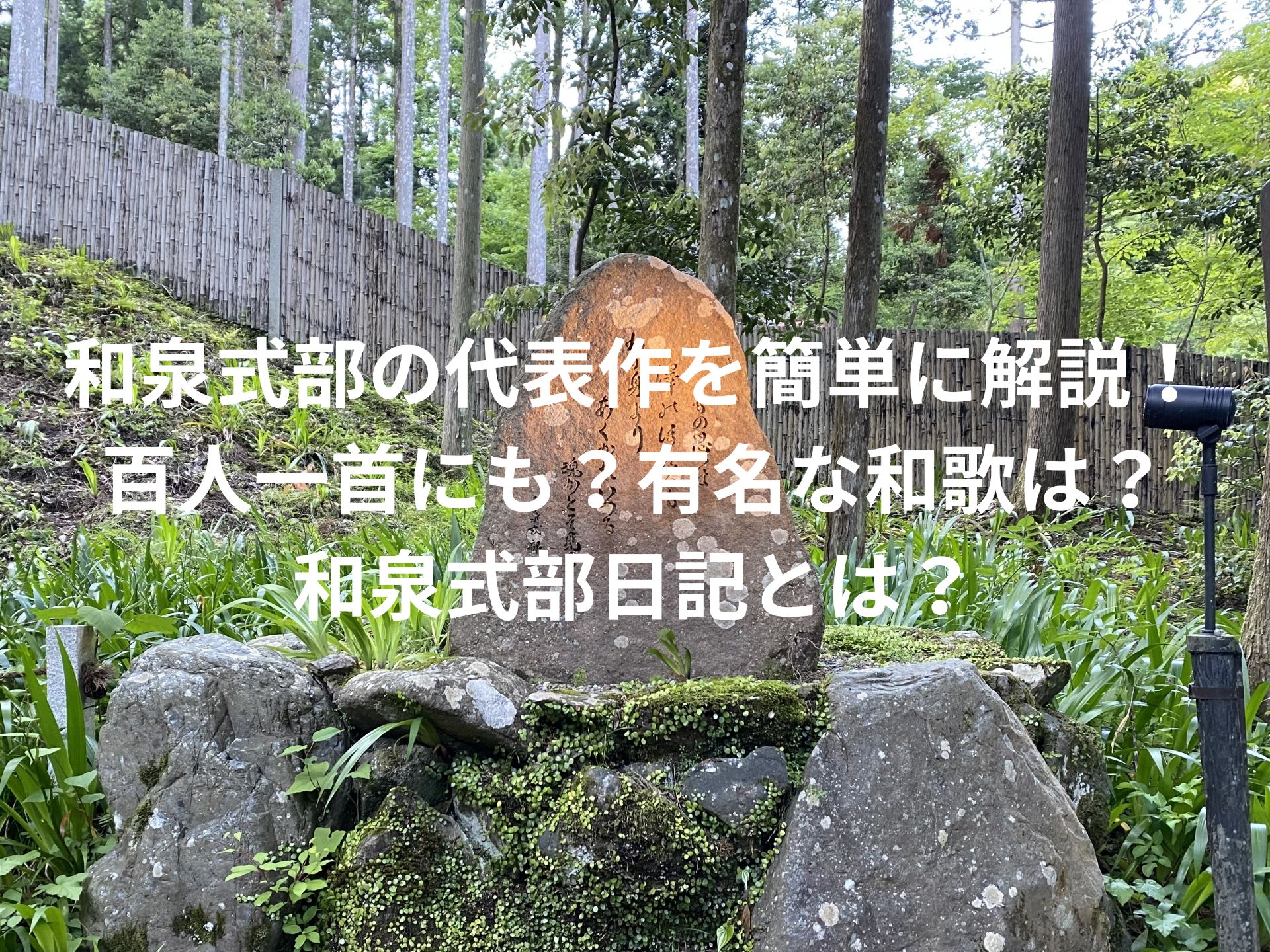藤原公任の百人一首の歌はどんな歌?意味や背景のエピソードなどを簡単に解説!
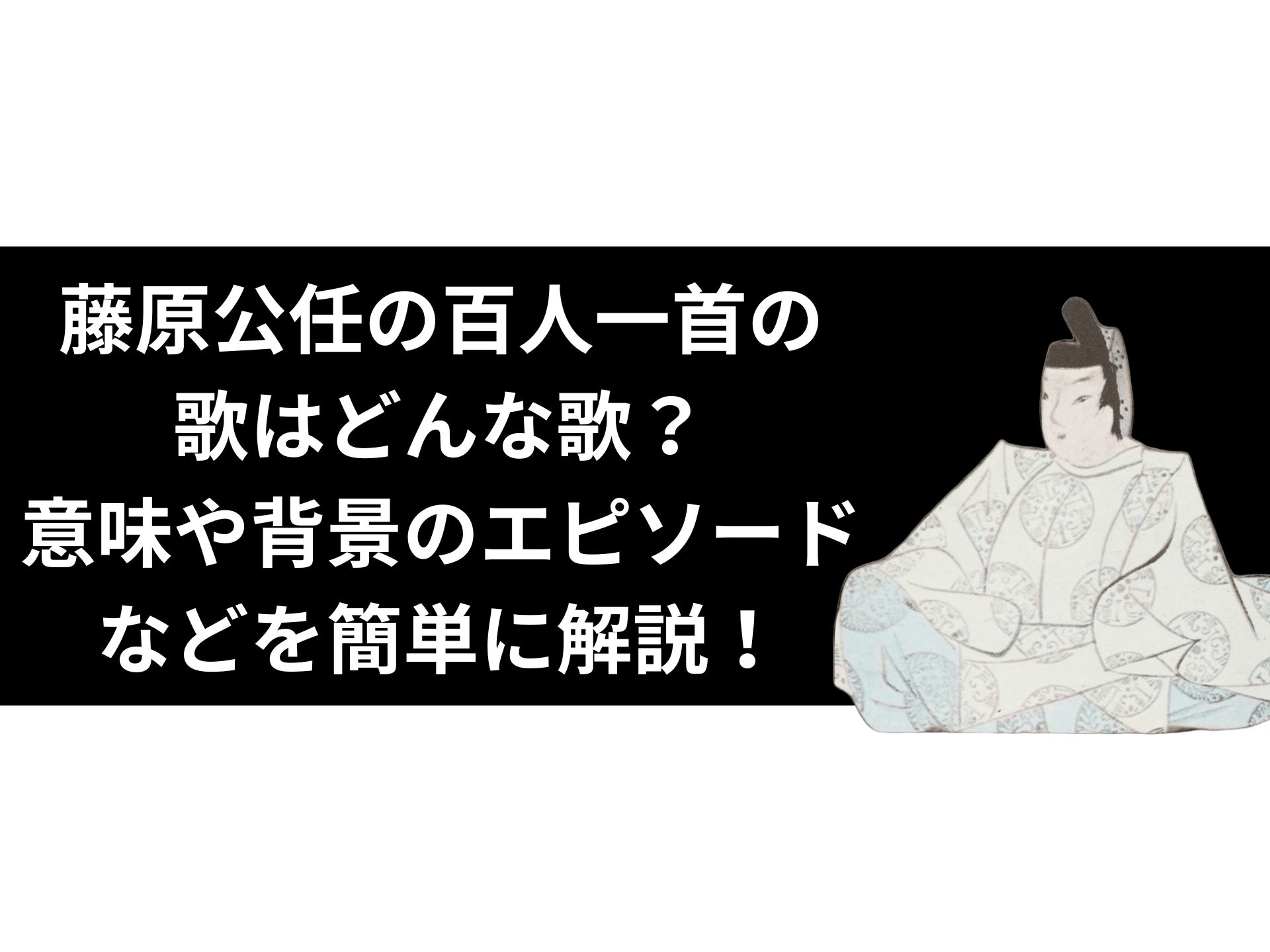
藤原公任(966(康保3)〜1041(長久2))は、平安時代中期に活躍した公卿です。
歌人としても知られており、中古三十六歌仙の一人としても数えられています。
また、2024年の大河ドラマ「光る君へ」では、町田啓太さんが演じられることでも話題となっています。
そんな藤原公任の百人一首の歌はどのような歌なのでしょうか?
この記事では、藤原公任の百人一首の歌について簡単に解説していきます。
目次
藤原公任の百人一首の歌の現代語訳や意味
藤原公任の百人一首の歌
「滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ」
現代語訳
滝の音が聞こえなくなってから久しくなりますが、その名声は今も流れ伝わっています
藤原公任の和歌は、百人一首の第55番目の和歌で、『千載集』より出典されています。
この歌は、藤原公任が藤原道長たちとともに嵯峨の大覚寺に出かけたときに詠んだものだと言われています。
これは、同行していた藤原行成の日記『権記』にも記されています。
大覚寺は、平安時代初期では嵯峨天皇の離宮となっており、広大な庭園の一画に滝がありました。
しかし、それから200年近い時が過ぎたため、藤原公任が見たときには滝は涸れてしまっていたのです。
そこで藤原公任は、この歌を詠み、「滝は涸れても名声は絶えない」としたわけですね。
藤原公任の洒落た知的さが伺える歌となっています。
藤原公任の百人一首の歌の表現技法
藤原公任の百人一首の歌の表現技法を詳しく見ていきましょう。
・「滝の音は」
「滝の流れ落ちる水音は」という意味で、この「滝」は『拾遺集』の詞書から、大覚寺にあった人工滝を指していることがわかります。
・「絶えて久しくなりぬれど」
「ぬれ」は完了の助動詞「ぬ」の已然形で、「ど」は、逆接の確定条件を表す接続助詞となっており、「〜けれども」という意味になります。
つまり、「聞こえなくなって久しくなるけれども」という意味になるのです。
・「名こそ」
「名」は、名声や評判を表します。
「こそ」は強調の係助詞です。
・「流れて」
「流れて」は評判が広まることを表しています。
「流れ」は滝の縁語です。
・「なほ聞こえけれ」
「なほ」は「それでもやはり」という意味の副詞です。
詠嘆の助動詞「けれ」は、前の「こそ」を結ぶ言葉で、「けり」の已然形となっています。
藤原公任の百人一首の歌の背景エピソード
藤原公任の百人一首の歌が詠まれた背景にはどのようなエピソードがあるのでしょうか?
この歌は、『千載集』より出典されており、その詞書には以下のように書いてあります。
「大覚寺に人あまたまかりたりけるに、古き滝を詠み侍りける」
(現代語訳)大覚寺に人がたくさん参上していたときに、古い滝を詠みました
ここからわかるように、この歌の舞台は嵯峨にある大覚寺です。
この大覚寺は、かつては嵯峨天皇の離宮でした。
そして、そこには広大な庭園があり、その庭園に造られたのが有名な大沢池で、その一角に小さな滝が築かれていました。
しかし、嵯峨天皇の死後、200年近く経ってしまい、藤原公任たちが訪れた際には、すでに庭園はすっかりと荒れ果て、滝の水も涸れてしまっていたのです。
そこで、藤原公任は、すでに涸れてしまっていた滝に、往時の美しさや流れる水音を思い、この和歌を詠みました。
この歌が百人一首に選ばれるなどにより有名になったことで、この滝は、歌からとって「名古曽(なこそ)の滝」と呼ばれるようになりました。
今でも大沢池には、「名古曽滝跡」の碑が立っています。
藤原公任はどんな人?簡単に解説!
藤原公任(ふじわらのきんとう) 966年(康保3年)〜1041年(長久2年)享年:76歳
父:藤原頼忠/母:厳子女王
妻:昭平親王の娘
子:定頼、良海、藤原教通正室、藤原尊子養女
藤原公任は、966年(康保3年)に父・藤原頼忠、母・厳子女王の間に誕生しました。
祖父も父も関白・太政大臣を務め、母、妻ともに二世の女王であり、また、いとこにも具平親王、藤原佐理、藤原実資などがおり、政治的にも芸術的にも名門の出身でした。
そのため、非常に将来が期待されていたと言われています。
その期待に応えるように、藤原公任は成長すると、博学多才な人物となりました。
漢詩・和歌・管弦楽の3つの才能を兼ね備えた「三舟の才」と評されることも。
この才能は他の追随を許さないほどで、時代を越えてもなお色褪せることのない優れた作品を多く残しました。
藤原公任に関するQ&A
藤原公任に関するQ&Aを簡単に解説していきます。
- 藤原公任は紫式部と恋仲だった?
- 藤原公任と藤原道長の関係は?
- 藤原公任の代表作は?
藤原公任は紫式部と恋仲だった?
実は藤原公任と『源氏物語』で有名な紫式部は恋仲だったのではないかとする説が存在します。
その根拠となるのが、『紫式部日記』にある以下のエピソードです。
あるとき、宮中で宴が開かれ、紫式部や同僚の女性も出席していました。
するとそこに、酔った藤原公任がやってきて、
「若紫(わかむらさき)はおいでですか?」
と紫式部に声をかけてきたのです。
この若紫とは、『源氏物語』のヒロイン・紫の上のことを指します。
藤原公任は、作中の人物と紫式部をかけたようですが、これは酔っ払ったうえでの軽い冗談である、というのが定説となっています。
しかし、一方で、「若紫」ではなく、「我が紫(わがむらさき)」=「私の紫式部」と呼びかけたのではないかとする解釈もあるのです。
「私の」が事実だとすると、2人は相当な深い仲であったのではないかと推測することができますね。
この藤原公任の呼びかけに対して、紫式部は
「(宴の場には)光源氏似の人もいないのに、紫の上がいるわけないじゃない」
と思い、藤原公任を無視したと日記に残しています。
この態度をどう解釈するかによって、2人の仲がどうであったのかの推測も変わってきますね。
なお、2人の関係について明記された史料はないので、未だに2人の仲は謎なままです。
藤原公任と藤原道長の関係は?
藤原公任と藤原道長は、祖父同士が兄弟のため、はとこの関係にあたります。
同い年のこともあり、お互いに意識しながら成長していただろうと考えられており、ライバルのような関係だったのではないかとされています。
諸芸において優秀であった藤原公任を見て、藤原道長の父は、
「公任の才には我が子は遠く及ばない。公任の影すら踏むことができない」
と嘆いていたそうです。
藤原道長の兄達がそれを聞き黙ってしまう中、藤原道長だけは、
「影など踏まず、顔を踏みつけてやる」
と答えたそうです。
このように、2人はお互いを意識しながら育っていったのでしょう。
成長してからは、藤原道長が権力を持ち、藤原公任がそれを支えるという形になりましたが、2人はお互いの才能を認め合っていたようです。
また、藤原公任と藤原道長に関わるエピソードでは、「三舟の才」が有名です。
あるとき、藤原道長が大堰川で舟遊びを催し、3つの舟を用意した上で、それぞれに管弦、漢詩、和歌の得意な人を乗せました。
藤原公任はいずれも堪能であったため、藤原道長からどの舟に乗るか尋ねられたのです。
そこで藤原公任は和歌の舟に乗り込み、以下のような歌を詠みました。
「小倉山 嵐の風の 寒ければ 散るもみぢ葉を きぬ人ぞなき」
(現代語訳)
まだ早い朝に強風が吹き荒れる山から吹き下ろす風が大変寒いので、木々は皆上着を着込むかのように錦のような紅葉をまとっていることよ
これを聞いた周りの人々は、藤原公任のことを絶賛します。
しかし、藤原公任は、漢詩の舟に乗っていれば、名声が一段と上がったろうに!と悔やんだそうです。
藤原公任の多才ぶりがよく現れているエピソードですね。
藤原公任の代表作は?
藤原公任の代表作には、百人一首の和歌の他にも以下のようなものがあります。
- 有識故実書『北山抄』
- 歌学書『新撰髄脳』
- 私撰和歌集『拾遺抄』
- 詩文集『和漢朗詠集』
特に、『拾遺抄』は、花山天皇が退位後に自ら編纂した『拾遺和歌集』の原型になったと言われています。
まとめ:藤原公任の百人一首の歌は、藤原公任の洒落た知的さが表れている
藤原公任の百人一首の歌は、すでに涸れてしまった滝の、在りし日の姿を思い起こしながら、その名声は涸れることはないと詠んだ歌でした。そこには、藤原公任の洒落た知的さがよく表れています。
今回の内容をまとめると、
- 藤原公任の百人一首の歌は、百人一首の第55番目の和歌で『千載集』より出典されている
- 藤原公任の百人一首の歌は、すでに涸れてしまった滝の在りし日の姿を思い起こしながら、その名声は涸れないと詠んだ歌だった
- 藤原公任の百人一首の歌からは、藤原公任の洒落た知的さが表れている
藤原公任の百人一首の歌には次のような意味も込められていたのではないかとされています。
「滝は涸れてもその名声は語り継がれている。ならば、私の歌もこの滝のように語り継がれたい」
いま現代を生きる私達のもとにもこの歌が届いていることから、藤原公任の願いは達成されていると言ってもいいのではないでしょうか。