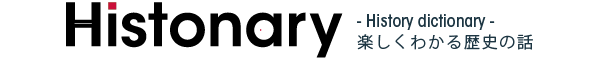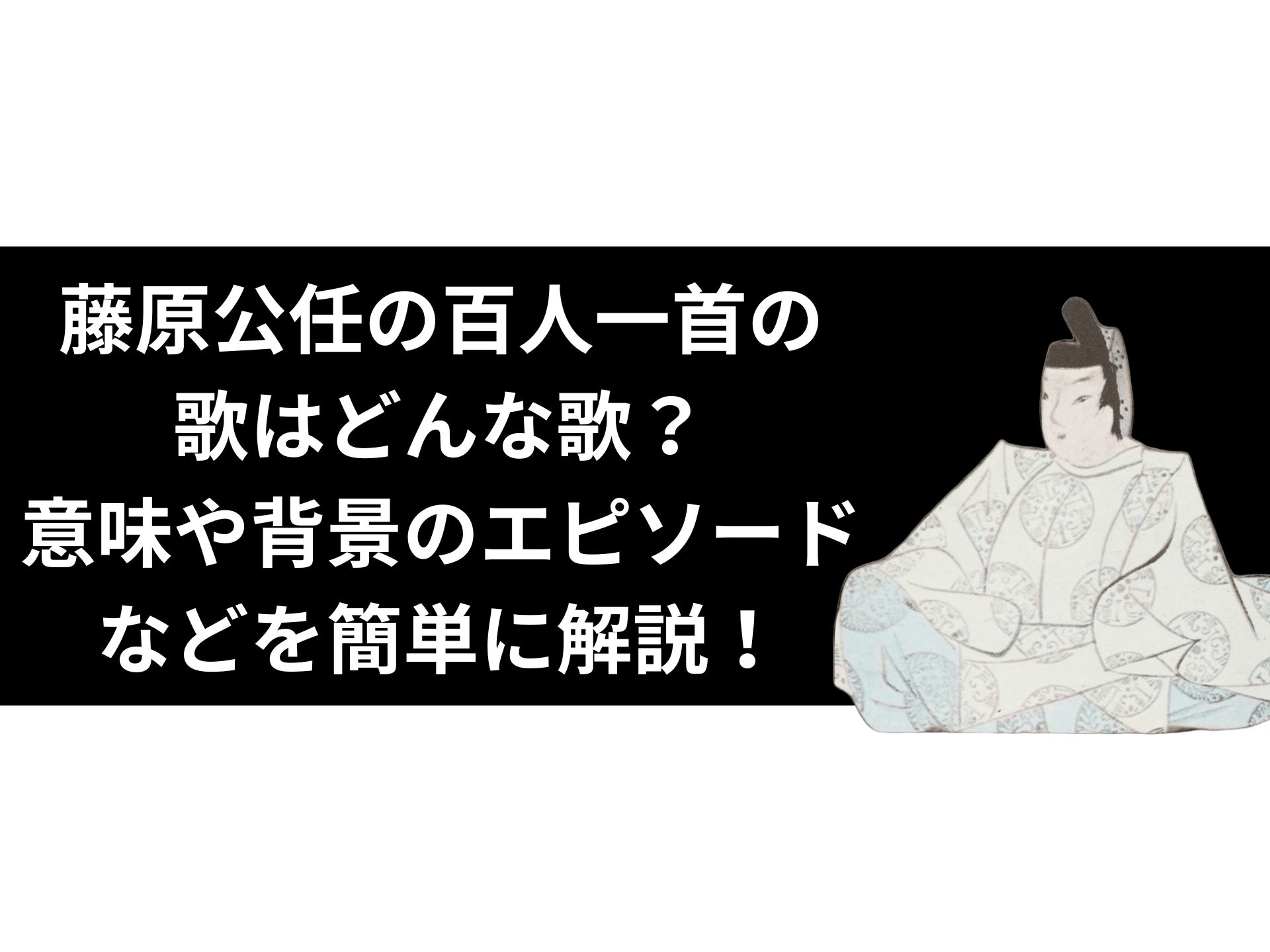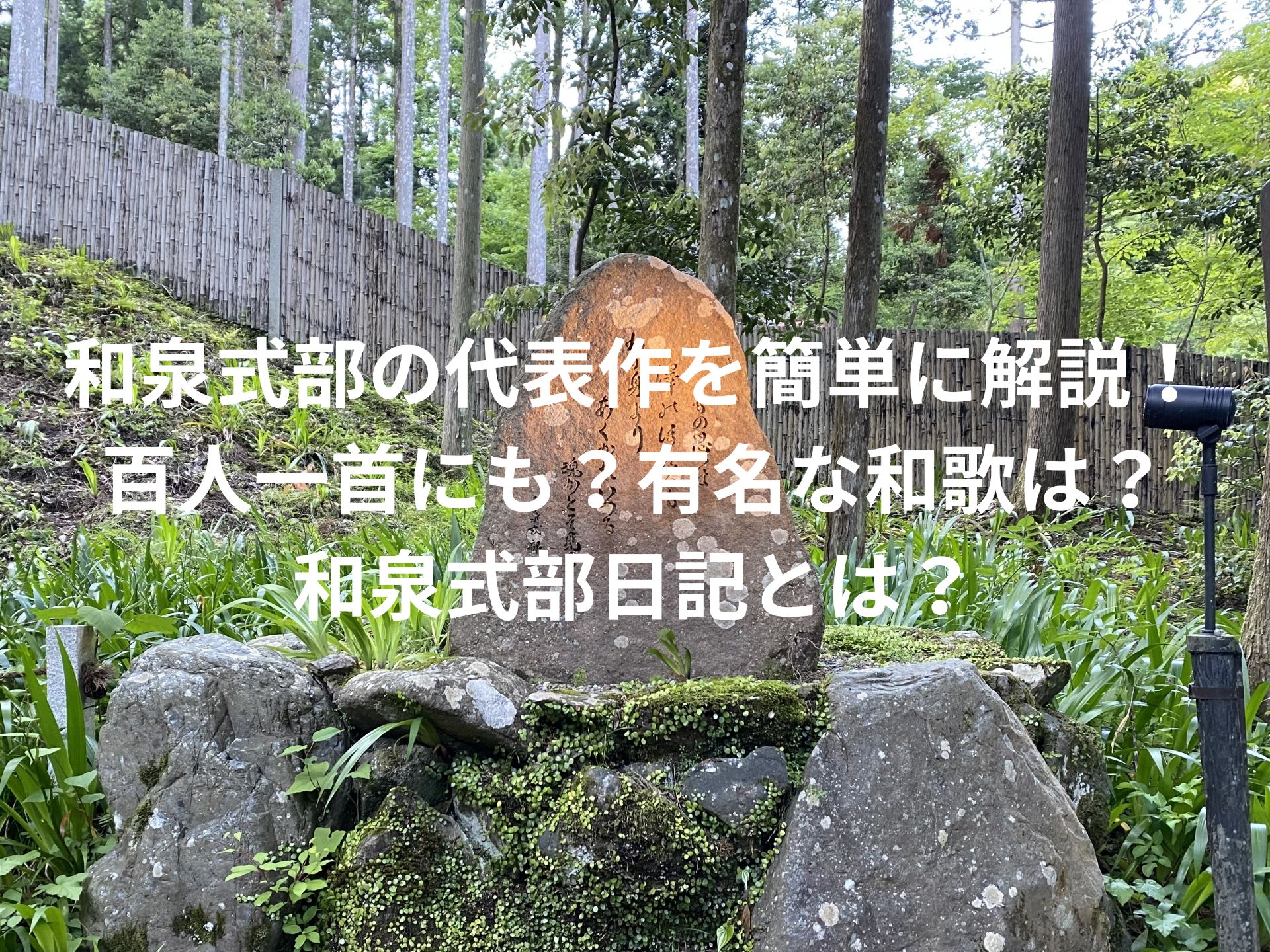藤原公任の家系図を簡単に解説!子孫は続いている?藤原道長との関係は?
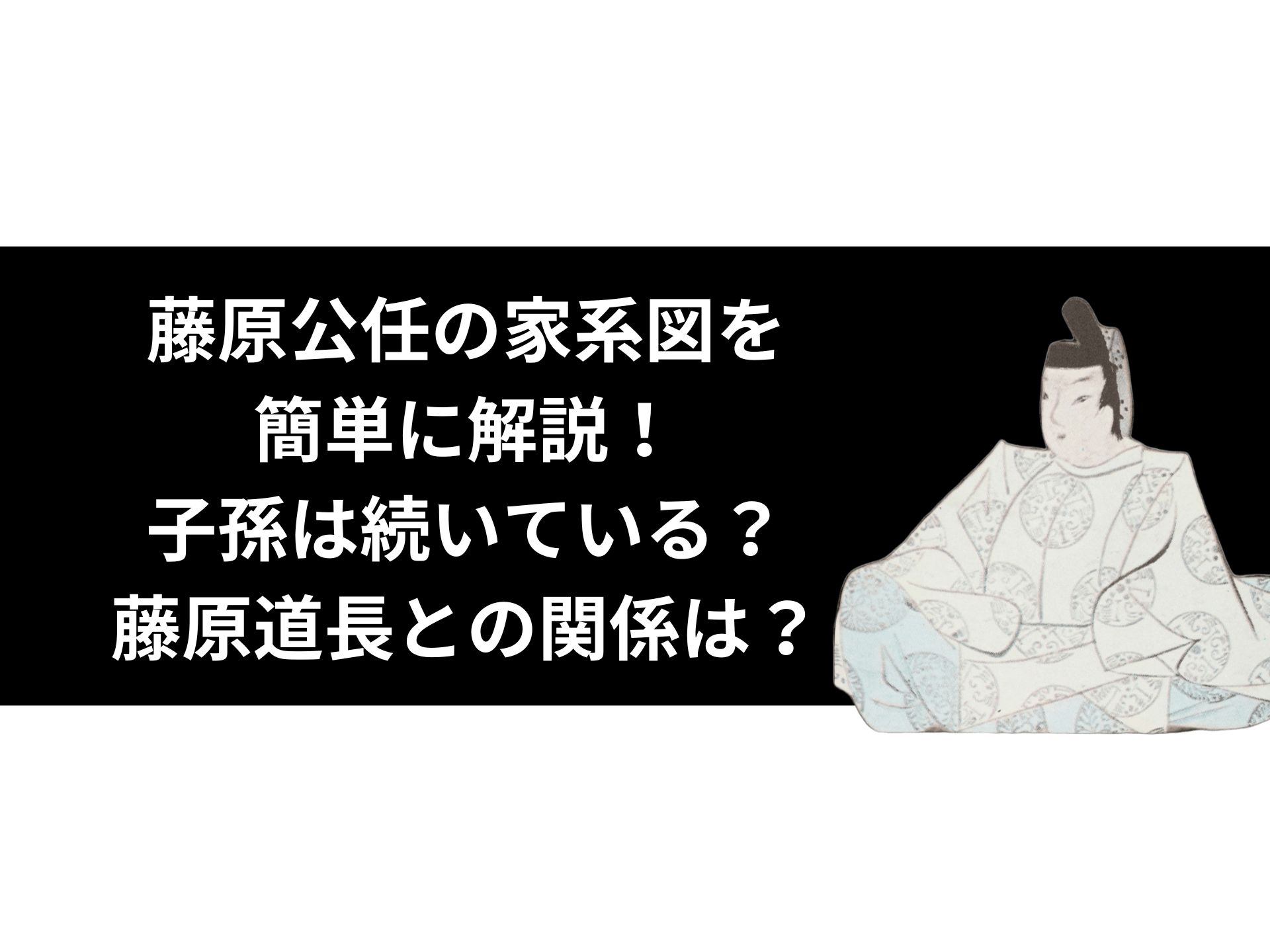
藤原公任(966(康保3)〜1041(長久2))は、平安時代中期に活躍した公卿です。
歌人としても知られており、中古三十六歌仙の一人としても数えられています。
また、2024年の大河ドラマ「光る君へ」では、町田啓太さんが演じられることでも話題となっています。
そんな藤原公任の子孫は現在まで続いているのでしょうか?
この記事では、藤原公任の家系図を見ながら、その子孫について簡単に解説していきます。
目次
藤原公任の家系図をわかりやすく解説!
【藤原公任の家系図】
藤原公任とはどんな人?
【藤原公任のプロフィール】
藤原公任(ふじわらのきんとう) 966年(康保3年)〜1041年(長久2年)享年:76歳
父:藤原頼忠/母:厳子女王
妻:昭平親王の娘
子:定頼、良海、藤原教通正室、藤原尊子養女
藤原公任は、966年(康保3年)に父・藤原頼忠、母・厳子女王の間に誕生しました。
祖父も父も関白・太政大臣を務め、母、妻ともに二世の女王であり、また、いとこにも具平親王、藤原佐理、藤原実資などがおり、政治的にも芸術的にも名門の出身でした。
そのため、非常に将来が期待されていたと言われています。
その期待に応えるように、藤原公任は成長すると、博学多才な人物となりました。
漢詩・和歌・管弦楽の3つの才能を兼ね備えた「三舟の才」と評されることも。
この才能は他の追随を許さないほどで、時代を越えてもなお色褪せることのない優れた作品を多く残しました。
藤原公任の子孫は途絶えてしまった
藤原公任は、妻・昭平親王の娘との間に4人(二男二女)の子供を残しました。
中でも定頼は、子を残し子孫を繋ぎましたが、その孫・公定の代で断絶してしまいます。
また、長女も藤原教通に嫁ぎ、後朱雀天皇の女御となる生子や後冷泉天皇の皇后となる歓子を生みましたが、どちらも子孫が続くことはありませんでした。
そのため、藤原公任の子孫は現在まで続くことはなく、途絶えてしまったのです。
藤原公任と藤原道長の関係は、はとこ
藤原公任と藤原道長は、祖父同士が兄弟のため、はとこの関係にあたります。
同い年のこともあり、お互いに意識しながら成長していただろうと考えられており、ライバルのような関係だったのではないかとされています。
諸芸において優秀であった藤原公任を見て、藤原道長の父は、
「公任の才には我が子は遠く及ばない。公任の影すら踏むことができない」
と嘆いていたそうです。
藤原道長の兄達がそれを聞き黙ってしまう中、藤原道長だけは、
「影など踏まず、顔を踏みつけてやる」
と答えたそうです。
このように、2人はお互いを意識しながら育っていったのでしょう。
成長してからは、藤原道長が権力を持ち、藤原公任がそれを支えるという形になりましたが、2人はお互いの才能を認め合っていたようです。
藤原公任は娘の死がきっかけで出家した
藤原公任は、自身の娘たちのことをたいそう愛していたようです。
その証拠に、晩年2人の娘を若くして亡くしてしまうと、出仕をやめ、満60歳で出家しました。
この藤原公任が出家したということは、都中にあっという間に噂が広まり、数多くの人が訪れてきました。
先に出家していた藤原道長も、その噂を聞き、藤原公任に法衣を贈ったそうです。
また、藤原斉信が藤原公任の元を訪れた際には、同じように娘を亡くしたものの出家の決心がつかないことを吐露し、2人で泣きながら会話をしたと言われています。
いかに娘のことを愛していたのかが伺えるエピソードですね。
藤原公任に関するQ&A
藤原公任に関するQ&Aを簡単に解説していきます。
- 藤原公任は紫式部と恋仲だった?
- 藤原公任の代表作は?
藤原公任は紫式部と恋仲だった?
実は藤原公任と『源氏物語』で有名な紫式部は恋仲だったのではないかとする説が存在します。
その根拠となるのが、『紫式部日記』にある以下のエピソードです。
あるとき、宮中で宴が開かれ、紫式部や同僚の女性も出席していました。
するとそこに、酔った藤原公任がやってきて、
「若紫(わかむらさき)はおいでですか?」
と紫式部に声をかけてきたのです。
この若紫とは、『源氏物語』のヒロイン・紫の上のことを指します。
藤原公任は、作中の人物と紫式部をかけたようですが、これは酔っ払ったうえでの軽い冗談である、というのが定説となっています。
しかし、一方で、「若紫」ではなく、「我が紫(わがむらさき)」=「私の紫式部」と呼びかけたのではないかとする解釈もあるのです。
「私の」が事実だとすると、2人は相当な深い仲であったのではないかと推測することができますね。
この藤原公任の呼びかけに対して、紫式部は
「(宴の場には)光源氏似の人もいないのに、紫の上がいるわけないじゃない」
と思い、藤原公任を無視したと日記に残しています。
この態度をどう解釈するかによって、2人の仲がどうであったのかの推測も変わってきますね。
なお、2人の関係について明記された史料はないので、未だに2人の仲は謎なままです。
藤原公任の代表作は?
藤原公任の代表作には、百人一首の和歌の他にも以下のようなものがあります。
- 有識故実書『北山抄』
- 歌学書『新撰髄脳』
- 私撰和歌集『拾遺抄』
- 詩文集『和漢朗詠集』
特に、『拾遺抄』は、花山天皇が退位後に自ら編纂した『拾遺和歌集』の原型になったと言われています。
まとめ:藤原公任の家系図からは、藤原道長とはとこであることがわかり、子孫は続かなかった
藤原公任は、時の権力者・藤原道長とはとこという関係にありました。そのため、お互いに意識しながら成長をしていったのです。また、子孫はあまり長くは続かず、現代までその血が繋がることはありませんでした。
今回の内容をまとめると、
- 藤原公任と藤原道長ははとこ
- 藤原公任は4人(二男二女)の子を残した
- 藤原公任の子孫は現在まで続いていない
権力者である藤原道長が自身の娘を出世のために利用していたのに対し、藤原公任は娘の死にショックを受け、出家してしまうほどでした。ここからも、2人の出世への執着心や家族に対する思いの違いが現れており、なかなか興味深いものですね。