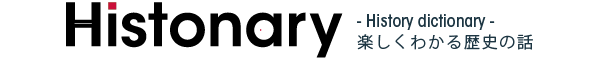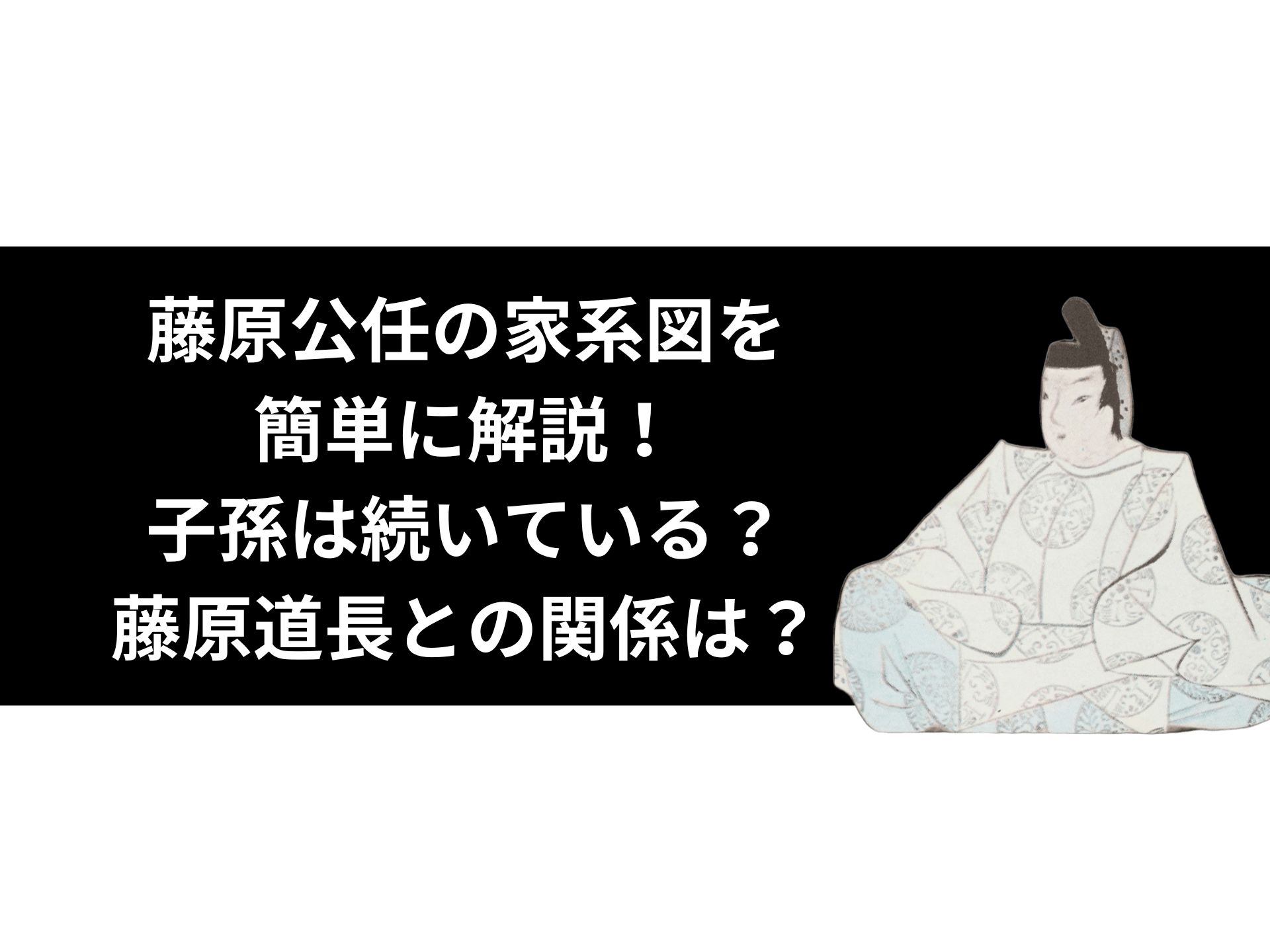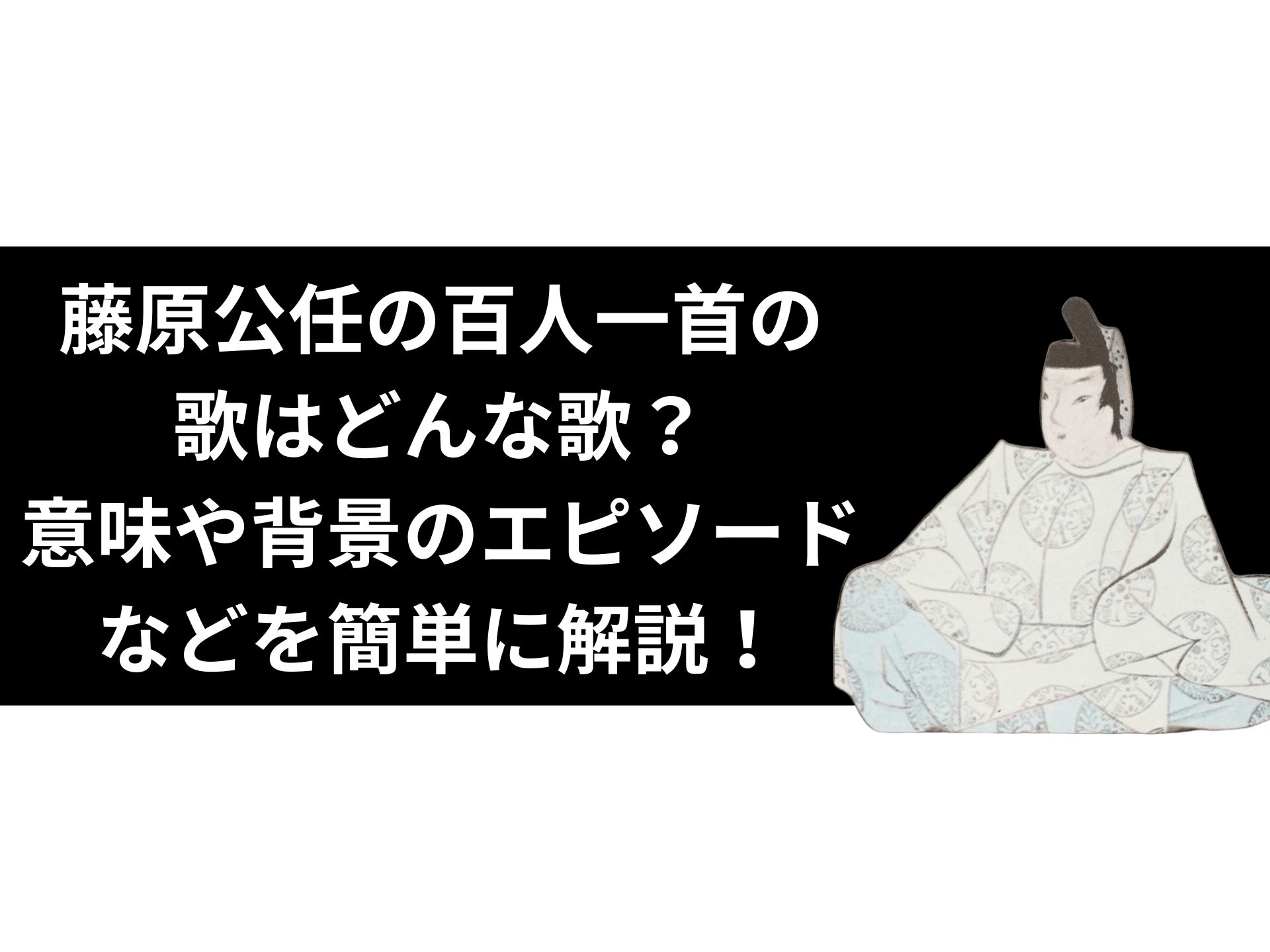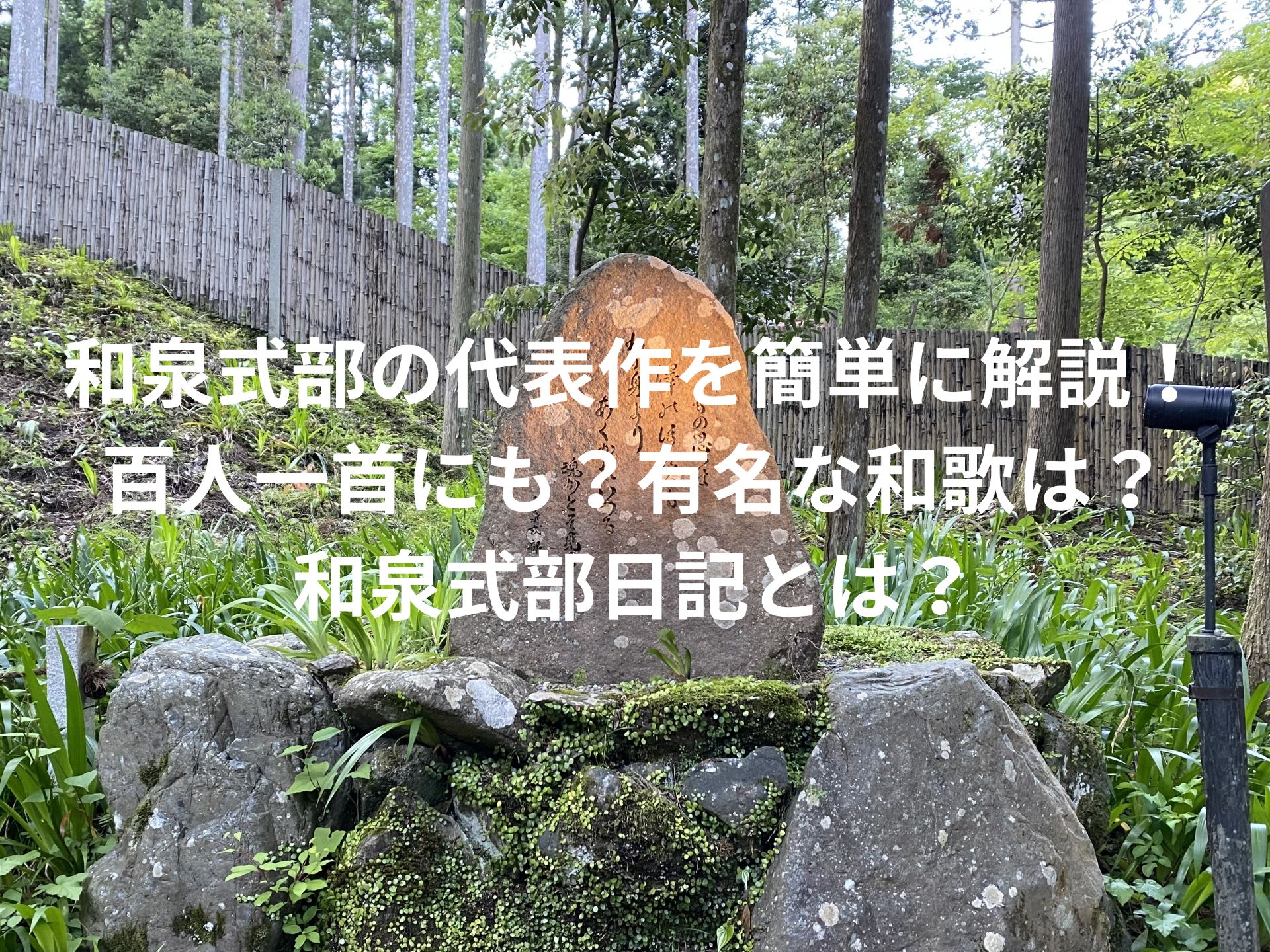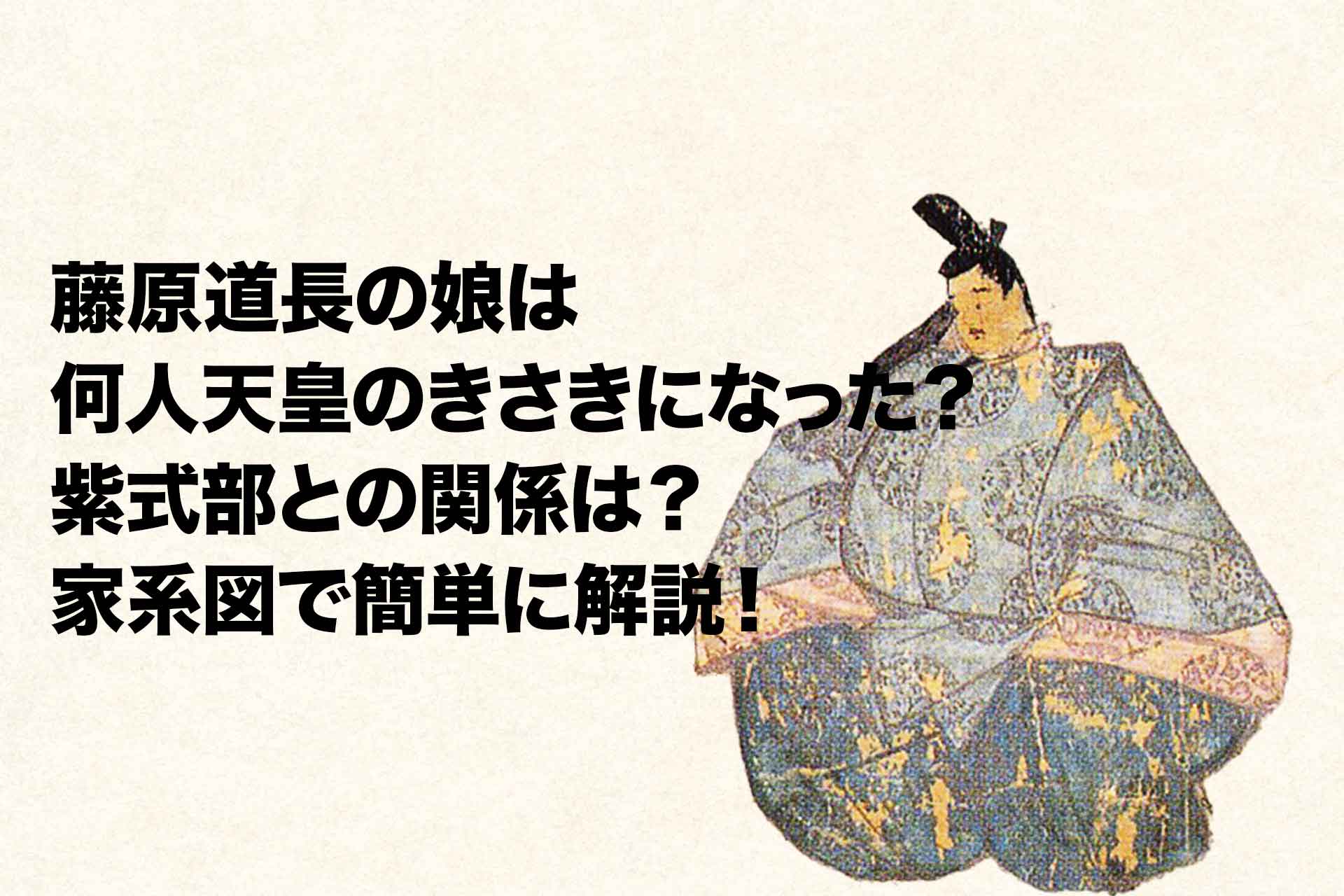藤原道長が摂政になったのはいつ?藤原北家が代々行ってきた摂関政治を簡単に解説!
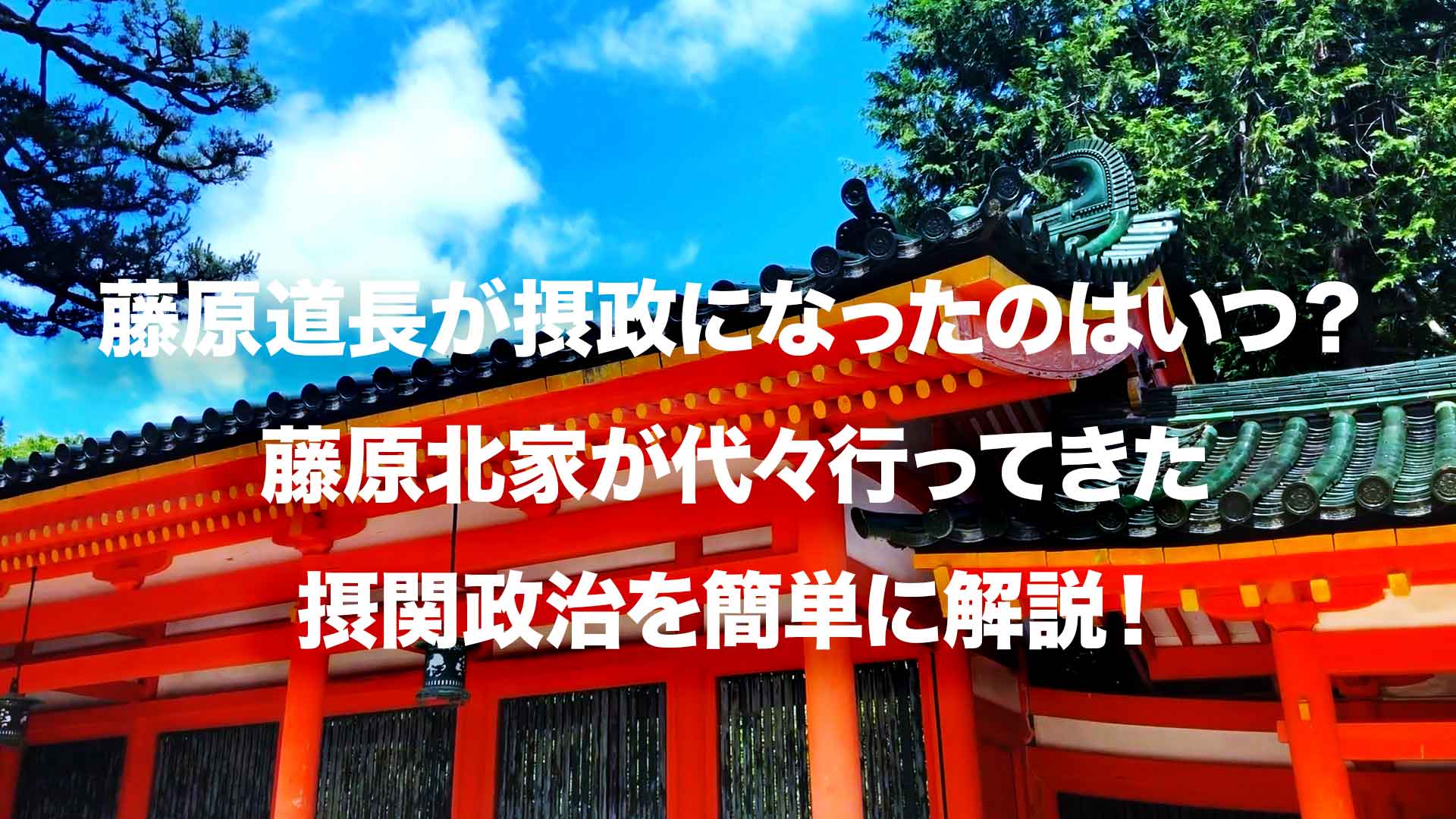
藤原道長(966(康保3)〜1028(万寿4))は、平安時代中期に活躍した公卿です。
2024年の大河ドラマ『光る君へ』では、柄本佑さんが演じられることでも話題となっています。
そんな藤原道長は、摂政となることによって権力を手中に収めました。
摂政にはいつどのようにしてなったのでしょうか?
この記事では、藤原道長がいつ摂政になったのかなどを簡単に解説していきます。
目次
藤原道長が摂政になったのはいつ?
藤原道長は摂政となることによって、権力を手中に収めました。
それでは、藤原道長はいつ摂政になったのでしょうか?
ここでは、藤原道長が摂政になったのがいつなのか?などを簡単に解説していきます。
摂関政治とは?
摂政は、天皇が幼い時に代わりに政治を行い、関白は、天皇が成人であるけれど政治を行う能力がない時に代わりに政治を行いました。
10世紀後半あたりから、藤原氏が代々摂政か関白の地位につき、11世紀前半の藤原道長・頼通の時代に摂関政治は全盛期を迎えました。
藤原道長は天皇の外戚となって摂政になった?
藤原道長は、一族内での権力争いに勝ち、内覧という摂政・関白に準ずる役職に就きます。
そして、その後にやったことが、自分の娘を天皇のきさきにするということです。
長女の彰子を、時の天皇・一条天皇へと嫁がせます。一条天皇には、すでに定子という后がいましたが、藤原道長は権力を使って無理やり彰子もきさきにしてしまいます。
その後、1010年(寛弘7年)に三条天皇が即位するのですが、眼病を患ったことを理由に藤原道長が退位させます。
退位させた結果、天皇になったのは敦成親王です。後一条天皇となるこの人物は、一条天皇の嫡男で、藤原道長の孫となる人物でした。
そのため、まだ幼い天皇を補佐するために、1016年(長和5年)に藤原道長が外祖父として摂政に任命されたのです。
つまり、藤原道長は天皇の外戚となることによって摂政になったのでした。
藤原道長はすぐに摂政をやめた?
せっかく摂政となった藤原道長でしたが、実はその翌年にはすぐに摂政の座を辞しています。
理由としては主に2つ挙げられます。
1つ目は、摂政という役職よりも、その後なった太政大臣のほうが、政府の人事権などを掌握しやすかったということ。自分の都合の良い人物を集めるには、摂政という役職では少し不便だったのです。
2つ目は、後継体制を固めるということ。
藤原道長は摂政の座を辞すると同時に、その座を息子の藤原頼通に譲っています。
さらに、藤原氏長者の座もこの時に一緒に譲っています。
こうして、息子に譲ることにより、藤原氏の独占体制を継続していこうと考えたわけですね。
以上、2つの理由から、藤原道長はあっさりと摂政の座を譲っているのです。
名声よりも実益を優先したのは、藤原道長らしい行動だと言えるでしょう。
藤原道長は関白にはなっていない?
藤原道長の日記が『御堂関白記』ということから、藤原道長が関白にもなっていたのではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、実は藤原道長は摂政にはなりましたが、関白にはなっていないのです。
それでは、なぜ『御堂関白記』という日記を書いていたのでしょうか?
この『御堂関白記』は、実は元々『御堂御日記』または『御堂御記』と呼ばれていました。
しかし、江戸時代以降、
「藤原道長ほどの人物であれば、当然関白になっていただろう」
という思い込みから、『御堂関白記』と呼ばれるようになったと考えられています。
このような思い込みから、藤原道長は関白になったと誤解されるようになってしまったのでした。
藤原北家は摂関政治を代々行ってきた?
藤原道長は、藤原氏の中でも、藤原北家に所属しています。
その藤原北家は、代々摂関政治を行ってきた家でした。
藤原北家はなぜ代々摂関政治を行ってきたのでしょうか?
ここでは、藤原北家について簡単に解説していきます。
藤原北家で摂関政治を行ったのは誰?
藤原北家で、一番最初に摂関政治を行ったのは、藤原良房です。
藤原良房は、842年に仁明天皇の実子であり、自らの甥かつ婿である道康親王を皇太子に立てることに成功し、その関係で太政大臣に就任します。
道康親王が即位して文徳天皇になると、次はその子である清和天皇が即位します。この清和天皇の母親は藤原良房の娘です。つまり、藤原良房は、9歳の清和天皇の外祖父となったというわけです。
この際、藤原良房は人臣で初めて摂政に任じられました。これが、藤原北家の摂関政治の始まりです。
これ以降、藤原北家では、同じように天皇の外戚となって摂政・関白の座に就き、権力を手にするものが増えていきました。以下、その例です。
- 藤原基経→摂政(関白)
- 藤原忠平→摂政・関白
- 藤原実頼→関白
- 藤原兼通→関白
- 藤原兼家→摂政・関白
- 藤原道隆→関白
- 藤原道長→摂政
- 藤原頼通→摂政・関白
藤原道長の息子の代で、藤原氏の摂関政治は終わりを迎えた?
藤原道長の娘で、一番最後に天皇になる子を産んだのは嬉子でした。
しかし、嬉子は子供を産んですぐに亡くなってしまい、さらに嬉子が産んだ後冷泉天皇には、皇子が生まれることはありませんでした。
また、藤原道長の息子・藤原頼通自身にもなかなか娘はできず、唯一の娘を入内させるも、皇女しか生まれませんでした。
つまり、天皇の外戚化計画はここで終わりを迎え、藤原氏の摂関政治はわずかな期間で終わりを迎えることとなってしまいました。
藤原道長の娘はどの天皇のきさきになった?
藤原道長は「一家立三后」を実現させた人物でした。
一家立三后とは、藤原道長が自身の娘を天皇や皇太子の妻として送り込み、一家から三人の皇后を出したことを指しています。
つまり、藤原道長は自身の娘を天皇や皇太子の妻にすることによって、天皇と親戚になったということですね。
- 第66代天皇:一条天皇→彰子(長女)
- 第67代天皇:三条天皇→妍子(次女)
- 第68代天皇:後一条天皇→威子(四女)
上記のように、藤原道長の娘は、4人天皇の妻にしました。
また、六女:嬉子も入内して皇子を産んでいますが、敦良親王が即位する前に亡くなってしまっているので、実際は天皇の后にはなっていません。
\藤原道長の娘に関しては、こちらの記事で詳しく解説しております/
まとめ:藤原道長は天皇の外戚になって、摂政になった
藤原道長は、自身の娘を天皇のきさきにしました。そして、その子が次代の天皇として即位することにより、天皇の外祖父として摂政となったのでした。
今回の内容をまとめると、
- 藤原道長は自身の娘を天皇のきさきにすることによって、天皇の外戚となった
- 藤原道長は、外戚となることによって、摂政の座を手に入れた
- 藤原道長は、摂政に就いた翌年には息子の藤原頼通に譲った
- 藤原道長は関白にはなっていない
藤原道長は、息子に摂政の座を早めに譲るなどして、後継体制をしっかりと整えたのに、結局その後皇子がうまく生まれなかったせいで、藤原氏の摂関政治は幕を閉じました。
子供は授かりものだといいますが、子供の性別によって終わってしまう権力は、なんて儚いものなのでしょうね。